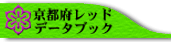| 選定理由 |
府内ではごく稀であり、過去30年間再確認されていない。 |
| 分布 |
本州(暖地)、四国、九州。
◎府内の分布区域
南部地域(京都市)。ただ、この同定には再考の余地が残る。 |
| 生存に対する脅威 |
森林開発。 |
| 必要な保全対策 |
府内唯一の産地では、すでに森林伐採により絶滅した。分類的に難しい種であり、再発見が望まれる。湿度の高い森林を維持することが保全には重要である。 |
| 形態 |
ホソバイヌワラビとカラクサイヌワラビとの中間的な種類であり、両者の雑種のヒサツイヌワラビとは胞子が正常かどうかが決め手である。それに加えて、トゲカラクサイヌワラビでは、小羽片の耳垂が発達すること、葉軸上に無性芽をつけないことも参考になる。カラクサイヌワラビでも小羽軸上に短い刺をつけることはあり、刺の有無は決め手にはならない。
◎近似種との区別
上記を参照。
◎参照 新日本植物誌 シダ;302頁(1992),日本の野生植物 シダ;pl.158-5,239頁(1999) |
| その他 |
日本固有種 |