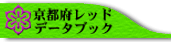レッドデータブックとは急激に減少したり、存続の危機に追いつめられた世界の野生生物種の状態についてのデータをまとめた情報集であり、最初の刊行は1966年の世界自然保護連合(IUCN)による哺乳類レッドデータブックであるとされている。その後、哺乳類以外の生物についてのレッドデータブックも順次発行されている。日本でも1986年に、「我が国における保護上重要な植物種および植物群落の研究委員会植物種分科会」によって『我が国における保護上重要な植物種の現状』(日本自然保護協会・世界野生生物保護基金)が作成されて後、環境庁によって1991年に『日本の絶滅のおそれのある野生生物(脊椎動物編・無脊椎動物編)』が発行され、以後植物、昆虫などが発行されている。またこれに呼応して、各都道府県からのレッドデータブックが順次発行されて、現在ではその計画をしていない都道府県はほとんどないという状態となっている。
しかしながら、これまでに発行されてきた各都道府県のレッドデータブックの中では、環境庁の植物群落に対応した植物群落や生態系などを取り扱った例はあるものの、自然現象にまで手を広げた例はごく稀である。京都府の場合には、京都の自然や古来から受け継がれてきた人の暮らし、あるいは文化を意識して、自然現象についての項目を付け加えることになった。自然現象というものをどのように定義し、また実際にも何を取り上げるかということは議論のあるところではあるが、同じく京都府レッドデータブックで扱われている地形・地質や生態系などと区分して、以下に取り上げたような項目を選択した。
また、自然現象については、現在の人間活動に依存して成立しているような点も多いために、今後の推移についても議論ができないような面がある(特に生物と同じような絶滅危惧のランク付けは不可能である)。他に例がないために十分に吟味できていない点もあるが、自然現象ごとにその性格などについて述べる。
|