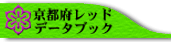| 選定理由 |
国内では北海道から九州のブナ帯に生息するが、どの産地でも個体数は少なく、良好な自然環境の指標として注目されている。府内では今のところ芦生とその近隣しか生息が確認されていない。これらの個体群は低標高のブナ林に隔離された遺存個体群として極めて貴重であるが、生息条件の限界にある産地のため個体数は非常に少なく、微妙な生息環境の変化で絶滅してしまうおそれが極めて高い。 |
| 形態 |
体長(大腮を含む)はオスで30〜55mm、メスで25〜40mm程度。体は厚みがある。光沢のない黒色で鞘翅上に点刻列はない。オスの大腮は全体に弧を描くように湾曲し、中央のやや前よりに斜め上にオオクワガタと似た向く内歯があり、それが和名の由来になっている。前胸背板は幅広く、側縁は丸みを帯び、後方1/3付近に小さな棘状の突起があり、それより後方で斜め内側に抉れるように切れ込む。メスでは前胸背板のこの内側への切れ込みがさらに著しい。雌雄とも脚が細長く、特にふ節が著しく長い。幼虫の頭部は黄褐色で頭幅5mm程度。頭蓋はやや面長で大腮は短く外側縁は直線的。体型は太短く、頭後方の胸部が襟巻き状に盛り上がる。頭部肛門孔は2葉片で背面側縁が直線的になる。
◎近似種との区別
最も近縁なアカカシクワガタとは、背面に光沢がない、腹面や腿節に赤い部分が全くない、オス大腮の内歯より先端部分には鋸歯がない、などの特徴で簡単に区別がつく。オスの大腮の形態がよく似ているオオクワガタとは、雌雄とも光沢のない黒色で小型個体でも鞘翅上に点刻列はない、眼縁突起(複眼のふちどり)がほとんど発達しない(オオクワガタでは複眼の前側4/5程度を覆う)、脚が細長く特にふ節が著しく長い、などの点で区別できる。 |
| 分布 |
国内では、ブナの分布とよく一致し、北海道(南部)、本州、四国、九州に分布するが、九州産は亜種キュウシュウヒメオオクワガタD. m. adachiiとして区別されてる。
◎府内の分布区域
府内 の記録は芦生と綾部市の頭巾山の2カ所のみであるが、これらの個体群は近隣府県の生息地から隔離された飛地的な分布地である。国外では朝鮮半島から中国東北部にも分布しているとされるが、変異など詳しいことは不明。 |
| 生態的特性 |
芦生では標高600m前後から本種の生息が見られるが、東北地方北部や北海道を除けば、普通、生息地は標高800〜1000m以上の山地に限られており、このような低標高での生息地は他に例を見ない。成虫は6月下旬頃から野外活動を始め、この時期には林床を歩行したりブナなどの巨大な倒木や立ち枯れに産卵に来ているメスを見かけることがあるが、この時期に産卵に来るメスは、前年の夏から初秋にかけて脱出した成虫が再越冬した個体である可能性が高い。本種の習性としては、8月中旬から10月にかけて昼間にヤナギなどの細枝にメスが大腮で傷をつけ、そこからしみ出る樹液を雌雄で吸うことが有名であるが、これらの個体のほとんどは新成虫と考えられる。成虫は気温の高い夏季には灯火にも飛来する。幼虫は非常に固いブナなどの巨大な白色腐朽の倒木や立ち枯れ中に見い出されるが、少し広めの部屋のような空間を作って穿孔している場合が多く、カミキリムシを思わせる目の細かな木屑の詰った食痕を残す。羽化後の新成虫はそのまま蛹室内で越冬する。 |
| 生息地の現状 |
芦生を除く福井県境の山地は伐採や植林が甚だしい。幸い、芦生の山林は京都大学の演習林であるため大規模な伐採等を免れてはいるが、林道建設やハイキング道の整備、下草刈りなどによって深淵部でも林内の乾燥化が著しいカ所が多く、多湿な環境を好む本種への影響が懸念される。また、芦生では、以前、複数の後食中の成虫が観察できた唯一のヤナギ群落が河川の氾濫がもとで失われてしまったため、活動中の成虫を観察することが極めて困難になってしまった。 |
| 生存に対する脅威 |
上記の要因に加えて、京都大学演習林であるため、本来、昆虫の採集などは制限されているはずの芦生でも近年の異常なクワガタムシブームの悪影響による商業目的の悪質な採集が目立ち、新たな脅威となっている。特に、生息環境の破壊にもつながるいわゆる「材割り採集」が横行しており、現存個体数の極めて少ない本種の存続に深刻なダメージを与えるおそれが多分にある。 |
| 必要な保全対策 |
原生林環境の保全が第一であるが、加えて、上述のような過剰な採集に対処した保全策が急務である。 |