トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地形 > 浜新田

| 分類 | 河川地形 |
|---|---|
| 細分 | 自然堤防 |
| 地域 | 京田辺市浜新田 |
| 選定理由 | 多数存在するが典型的な形態を示し。保存が望ましい地形。地域において生活と密着した存在であるものやランドマークとして親しまれている地形。 |
| 概要 | 河川が氾濫を起こすと、河道近くには相対的に粗粒な土砂が、河道から離れた低地には細粒な粒子が堆積する。このため、河道に近い場所には、その背後の低地と比較してわずかながら高い土地が形成されることが多い。 日本では、河道の両岸は多かれ少なかれ人工的に手の加えられた堤防が建設されている場合がほとんどである。規模は異なるものの、自然状態の河川でも、洪水時の作用によって人工堤防に類似の微高地が形成される。このような地形は自然堤防と呼ばれる。形成時には河道の周囲に連なって位置していた自然堤防も、繰り返される洪水氾濫によって河道の位置が変化すると、その連続性が失われ、周辺低地の中に島状に点在するような分布形態をとることが多い。自然堤防は、周辺低地(氾濫原または後背地)と比べるとわずかに高く、そのために地下水位がやや低い。また構成物も相対的に粗粒な物質からなるので、低地よりは水はけがよい。このため、後背地に水田が卓越するような地域でも、自然堤防は集落や畑地として利用されている場合が多い。 山城盆地を流れる木津川の低地では、至るところに自然堤防を観察することができ、京田辺市浜新田の自然堤防はその典型例の一つである。後背地は水田として利用されているが、孤立した自然堤防上は集落や畑として利用されている。写真で示したように、両者の間には2mほどの高さの違いが認められ、洪水に対する安全度が相対的に高いため、江戸期初期に集落が成立したと考えられる。 本地域では、低地の微地形と対応した伝統的な土地利用形態が残されている。しかしながら周辺では、新たな宅地開発が進行している。水害の危険性も考えると、自然堤防よりも低い後背地の宅地開発などは、極力避けるべきである、今後の土地利用に際しても、地形の特性に配慮した対応が望まれよう。 |
文献 谷岡(1964)
執筆者 高田将志

2.5万分の1 田辺

京田辺市浜新田の自然堤防
トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地形 > 浜新田
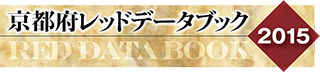
.gif)