トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地形 > 質志鍾乳洞

| 分類 | 組織地形 |
|---|---|
| 細分 | 鍾乳洞 |
| 地域 | 船井郡京丹波町字質志大崩12-1 |
| 選定理由 | 京都府の自然を代表する典型的かつ貴重な地形。教育上、地形研究上注目すべき地形。 |
| 概要 | 高屋川最上流の標高約400mの質志一帯には丹波層群の緑色岩(玄武岩溶岩)中にはさまれた石灰岩が露出しており、小規模なカルスト地形が発達する。ここには府下で唯一の鍾乳洞がある。 今から2億年前頃、熱帯の海域に形成されていた珊瑚礁に起源をもち、日本列島に付加された石灰岩である。この質志石灰岩からは二畳紀前期のフズリナやコノドント化石が発見されている。秋吉台(山口県)や伊吹山(滋賀県)はこのような礁石灰岩の大規模な例である。石灰岩が侵食によって地表付近に表れ、長い年月をかけて地下水による溶解作用を受け、現在の鍾乳洞ができあがったと考えられている。 この鍾乳洞は1927(昭和2)年に発見された。入口は山の中腹にあって、洞窟の延長は120m、入口から最深部までの深さは25mで、四つの部分からできている。発見当時は鍾乳石や石筍などがあったようであるが、現在では破損や破壊されているものもある。 |
| 関連法令 | 京丹波町文化財保護条例(町指定天然記念物) |
文献 地学団体研究会京都支部(1982)、木村ほか(1989)
執筆者 塩見良三

2.5万分の1 菟原

京丹波町質志鍾乳洞内部
トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地形 > 質志鍾乳洞
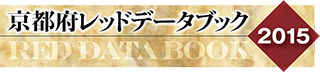
.gif)