ススキ群落
| 分類 | ススキ草原 |
|---|---|
| 特徴 | ススキ自体はやや乾燥した日のよく当たる立地に生える多年草で、人里などで広く見られる植物である。ススキ群落は、家畜の放牧や屋根ふき用のススキ(カヤ)などを得るために、火入れをしてカヤ場と呼ばれるススキ草原を作るもので、昔は多くの集落の近くの山の平坦地等に作られていたものであるが、近年ではススキの必要がなくなったために、ほとんど姿を見なくなっている。日本では原植生が草原という例はごく少ないが、管理されていたススキ群落があるために、ススキ群落の中でススキと共に生育してきたような草本類がある。多くの場合には、ヤマハギ、ワラビ、オカトラノオ、ニガナ、シラヤマギクなど多くの植物が混じり、生育している。これも定期的に刈り取られたり、火が入ったりするような人の管理に適応して、ススキ群落として成立しているものである。 |
| 分布 | 暖温帯及び冷温帯の日本全土に分布する。元の植生を伐採などすると、必ずといっていいほどにススキが現れ、放置すると定着する。府内でもほぼ全域で見ることができる。 |
| 保存に対する脅威 | かつては各地で見られたが、現在ではほとんど見られなくなっている。人が刈り取ったり、火を入れることで成立している群落であるために、保全するということは、毎年同じ様に人手を入れることが必要となり、放置すると、木本植物等が入ってきて、数年でススキの勢いは衰える。そのため、ススキ群落として保全するのであれば、毎年誰かが、どの様な組織で管理をしていくのかということを決めて、実行することが必要となる。近年では、カヤを得るため、火入れによるススキ群落の維持が行われている地域もある。 |
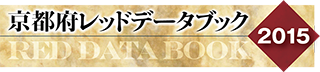
.gif)