
| 選定理由 | 本種の生息に必要な氾濫原環境が河川改修、都市化や圃場整備によって激減しており、個体群が縮小している。 |
|---|---|
| 形態 | 体長5cm前後。体はゼゼラ同様、細長く、前部がやや縦扁し後部が側扁する。体側と背中線には淡黒色の斑紋が並ぶ。ゼゼラとくらべて眼径が小さく、体高、尾柄高が高い。背鰭は、オスで発達し、外側に膨らみ鋸歯状を呈する。メスや未成魚は直線状の外縁を示す。繁殖期になるとオスは斑紋が薄くなり、銀黒色を呈し、胸鰭の前縁には大きめの追星が2列並んで生じる。側線鱗数は34~35。 |
| 分布 | 琵琶湖・淀川水系にのみ分布する。 ◎府内の分布区域 桂川、宇治川、木津川の中下流域。 |
| 生態的特性 | ワンド、タマリ、二次流路、農業水路などの流れの緩やかな砂泥底から泥底に生息する。産卵期は4~7月上旬でオスはヨシ、ガマなどの抽水植物や陸性植物の根になわばりを持ち、そこにメスがやってきて卵を産みつける。雌雄とも満1年で成熟する。 |
| 生息地の現状 | 府内では、桂川、宇治川、木津川の中下流域に広く分布していたと考えられるが、現在、宇治川では確認できない。桂川下流域と木津川の一部で個体数の多い地区があるが、生息環境は悪化しており、予断を許さない状況である。 |
| 生存に対する脅威 | 圃場整備や宅地開発、工業化などの都市化による水田地帯の消失、河川改修による堤外氾濫原のワンド、タマリの消失・環境悪化に加え外来魚による食害が挙げられる。 |
| 必要な保全対策 | ワンド、タマリの環境改善、二次流路の確保、水田地帯の開発抑止、河川本流との接続の維持、外来魚の駆除などを行なう必要がある。 |
| 改訂の理由 | 2010年に新種として発見される。 |
| その他 | 日本固有種 |
文献 Kawase and Hosoya(2010)、川瀬、木村(2012)
執筆者 川瀬成吾
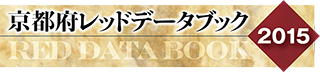
.gif)